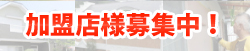近年、マイホームの外壁塗装を、DIY(自分自身で行うこと)で挑戦する方が増えています。
「専門業者に頼むと費用が高いので、自分で塗れば安くできるのでは?」とお考えの方も多いでしょう。
確かに、外壁塗装は塗料と道具を揃えれば、自分で行うことも不可能ではありません。
しかし、高所での危険作業や仕上がりの品質など、注意しなければいけないポイントも数多くあります。
この記事では、外壁塗装をDIYで行うことのメリット・デメリットから、具体的な手順、必要な道具、そして失敗しないための注意点まで、専門家の視点で徹底解説します。
DIYが向いているケースとプロに任せるべき場合の見極め方についても触れていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
外壁塗装をDIYするメリット・デメリット

まず、外壁塗装をDIYで行うことのメリットとデメリットを確認しておきましょう。
DIYには、費用面などの大きな利点がある一方で、時間や安全性の面で注意すべき点も多く存在します。
以下に、DIYと、専門業者に依頼した場合の主なメリット・デメリットを整理しました。
DIYのメリット

費用を大幅に節約できる
DIYで外壁塗装を行えば、業者に支払う人件費や中間マージンが不要なため、外壁塗装工事費用の半額程度に抑えられる場合もあります。
例えば、30坪程度(外壁面積約120㎡)の住宅を、シリコン塗料で塗装する場合、業者に依頼すると約100万円ですが、DIYなら、塗料代約40万円+道具代数万円+足場代約15〜20万円程度で済み、合計50〜60万円前後にできる可能性があります。
自分の好きなタイミングで作業できる
業者に頼むと、工事日程の調整や打ち合わせが必要ですが、DIYなら自分のペースで好きな時に塗装作業を進められます。
天気の良い週末に少しずつ作業したり、自身の都合に合わせてスケジュール管理できる点は、DIYの利点です。
小さな部分補修に対応しやすい
壁の一部の塗装剥がれや、小規模なひび割れ補修など、わざわざ業者を呼ぶほどでもない小さな補修であれば、自分で手軽に塗装してしまえるというメリットもあります。
ちょっとした塗り直し程度ならDIYで済ませられるでしょう。
施工過程を楽しめる
日曜大工が趣味の方にとって、家の塗装作業そのものが楽しい作業になる場合もあります。
自分の手で家が綺麗になっていく達成感は、DIYならではの楽しさと言えるでしょう。
家への愛着が湧く
自分で手間ひまかけて塗装した家は、一段と愛着が湧くものです。
苦労して塗り終えた後は、我が家をより大切にしようという気持ちが高まるかもしれません。
DIYのデメリット

非常に時間と手間がかかる
外壁塗装は、家全体の大掛かりな作業です。
プロの職人が2〜3人がかりで行っても約2週間はかかる作業を、素人が一人で行うと、数ヶ月かかることもあります。
平日は仕事で週末しか作業できない場合、完了までに想定以上の長期間を要するでしょう。
作業中は、足場を長期間借りる費用も発生し、塗料の臭いが近隣に漂う期間も長引くことになります。
高所作業に危険が伴う
外壁塗装では、2階や屋根付近の高所作業が避けられません。
足場を組まずに脚立などで無理に作業すると、落下による重大な事故につながる恐れがあります。
実際、プロの職人でも足場からの墜落事故が起きる作業です。
安全帯やヘルメットなどの万全な対策が必要で、転落によるケガはもちろん、最悪の場合死亡事故のリスクもあります(高所作業の危険性についてはこちらの記事もご覧ください。)。
仕上がりの品質に不安がある
塗装の技術や経験が不足していると、塗りムラができたり、塗膜が十分な厚さにならなかったりして、仕上がりが不均一になる可能性があります。
下地処理が不十分だと、数年で塗装が剥がれてしまうケースもあります。
プロのように美しく長持ちする塗装に仕上げるのは簡単ではありません。
近隣トラブルのリスク
塗装作業では、高圧洗浄時の汚水や塗料の飛散、作業音などで近隣への迷惑が生じる場合があります。
特に、エアスプレーで塗装すると塗料ミストが風で飛び、ご近所の車や壁に付着してクレームになるケースもあります。
養生シートや、飛散防止ネットを設置しないDIY塗装は、近隣トラブルのリスクが高まります。
想定外の出費が発生する可能性
DIYでうまく塗れずに塗り直しになったり、塗料を買い足したりすると、結果的に費用が嵩む恐れがあります。
作業期間が延びれば、足場レンタルの延長料金が発生することもあります。
また、途中で「やはり無理だ」となって業者に仕上げを依頼すると、二度手間分の余計な費用がかかってしまうでしょう。
以上のように、DIYには費用面のメリットがある反面、大きな労力とリスクが伴います。
「外壁塗装をきれいに長持ちさせたいが自分での作業は不安…」という方は、無理をせずプロの塗装業者に任せるのが安心です。
外壁塗装DIYを始める前の準備・必要な道具

DIYで外壁塗装を行うと決めたら、実際の作業に入る前にしっかりと準備を整える必要があります。
ここでは、作業前に確認すべきポイントと、揃えておくべき道具類について説明します。
足場と高所作業への備え

最も重要なのは、作業用の足場をどう確保するかです。
外壁全体を塗装するには、高所でも安定して作業できる足場が不可欠です。
専門の足場業者に依頼すれば、住宅周囲に金属製の足場を組み立て、防護ネットで覆ってくれるため安全性と作業効率が格段に向上します。
足場設置には15〜20万円程度の費用がかかりますが、足場を省略することは安全面から絶対に避けましょう(予算がないからと足場なしで施工する危険性についてはこちらの記事も参照してください)。
もし、DIYでどうしても費用を抑えたい場合でも、「足場の組立だけ業者に依頼する」という方法があります。
プロに足場だけ設置・解体してもらえれば、安全で安定した作業環境を確保でき、飛散防止ネットも張ってもらえます。
当然、費用は発生しますが、自分は塗装作業に専念できるメリットがあります。
ただし、足場レンタル期間が長引くと延長料金がかかる点には注意しましょう。
なお、法律上も、高さ5m以上の足場組立・解体作業には有資格者の指揮が必要と定められており、無資格の素人がいきなり安全に組めるものではありません。
2階程度の高さでも脚立だけでの塗装は非常に危険です。
安全帯やヘルメットを必ず着用し、少しでも不安がある場合は、無理をせずプロに任せる決断も大切です。
外壁塗装DIYに必要な道具・材料

次に、DIY塗装を行うために揃えておくべき主な道具と材料を一覧にします。
- 高圧洗浄機(家庭用電動洗浄機)やデッキブラシなどの洗浄道具
- バケツ、ホース、中性洗剤、デッキブラシ、ワイヤーブラシ等の清掃用具
- 外壁のひび補修用のコーキング材(シーリング材)とヘラ
- サンドペーパー(紙やすり)や皮スキ(スクレーパー)などのケレン道具(サビ落とし・古い塗膜剥がし用)
- 養生シート(ビニールシート)やマスキングテープ、マスカーなど養生用品
- ローラー各種(広い面積用の太いローラーと、細部用の小型ローラー)、延長用ローラーポール
- 刷毛(はけ)各種(細部塗装や縁取り用に幅の異なるものを数本)
- 塗料用の下げ缶やペイントトレイ(塗料を入れてローラーに含ませるバケツ)
- 下塗り用塗料(シーラー、フィラー、錆止めプライマー等、下地に応じたもの)
- 上塗り用塗料(仕上げ用塗料。水性/油性や塗料の種類を外壁材や予算に応じて選定)
- シンナー(希釈用。油性塗料を使う場合)
- 安全保護具(ヘルメット、ゴーグル、防塵マスク、厚手の手袋、安全帯(ハーネス)、滑りにくい靴など)
以上のような道具類が必要です。
初めて一から揃える場合は、すべて購入する必要があり、塗料代以外にも道具代として数万円程度の出費を見込んでおきましょう。
道具を購入する際は、安価なものより使いやすい品質の良いものを選ぶことがポイントです。
安物のハケやローラーでは、毛が抜けたり、塗りにくかったりして、作業効率が落ちる場合があります。
購入後は本番作業の前に使い方に慣れておくことも大切です。
外壁塗装DIYの手順(基本的な流れ)

ここからは、外壁塗装をDIYで行う際の基本的な作業手順を、具体的に説明します。
プロに依頼する場合でもDIYでも、作業の順序自体は基本的に同じです。
「足場設置」「洗浄」「下地処理」「養生」「下塗り」「中塗り・上塗り(二度塗り)」「片付け」という流れで進めます。
それでは、一つひとつの工程を見ていきましょう。
1. 足場の設置

外壁塗装の作業を安全かつ効率良く行うため、まず足場を設置します。
一般的には、専門の足場業者に依頼して鉄パイプ製の足場を家の周囲に組み立ててもらいます。
併せて、飛散防止用のメッシュシート(養生ネット)で家全体を覆ってもらうことで、洗浄時の汚水や塗料の飛散が近隣に及ぶのを防ぎます。
足場設置には大きな音が伴い、作業車両も家の周りに駐車する必要があるため、近隣住民へ事前に工事日程を知らせておくと良いでしょう。
繰り返しになりますが、安全のため、足場は必ず組んで作業してください。
足場がない状態での高所作業は、非常に危険であり、プロでも足場なしで外壁全面を塗装することはまずありません。
足場を設置せずに、脚立のみで2階部分を塗ろうとすると、塗るたびに何度も上り下りして脚立を移動させねばならず作業効率も極めて悪くなります。
安全かつスムーズに作業を進めるためにも、DIYであっても、足場の設置を省かないようにしましょう。
※足場の組立・解体作業は高所での危険作業のため、必ず有資格者に行ってもらってください。
2. 外壁の洗浄・乾燥

足場を設置したら、塗装前の下準備として外壁の洗浄を行います。
外壁には、ホコリや土汚れ、カビ・コケ等が付着していますので、これをしっかり落としておかないと塗料が密着せず、後々塗膜剥がれの原因になります。
家庭用の高圧洗浄機があればそれを使い、ない場合はデッキブラシで水洗いしましょう。
水だけで落ちない頑固な汚れには、中性洗剤を使用し、ブラシでこすって洗い落とします。
特に、軒下や日陰部分には、カビやコケが発生しやすいので、念入りに洗浄してください。
一通り洗浄が終わったら、外壁を十分に乾燥させます。
濡れたままの壁に塗装すると密着不良を起こすため、最低でも丸一日以上は乾燥時間を取りましょう。
洗浄翌日以降に塗装作業を開始するのが理想です。
途中で雨が降った場合も乾燥をやり直す必要があります。
高圧洗浄中や乾燥中は、足場や周囲が滑りやすくなっていますので、安全に十分配慮してください。
3. 下地処理(ひび割れ補修・錆落とし等)

洗浄・乾燥が終わったら、塗装前に必ず行うべきなのが、下地処理です。
外壁の下地に劣化やダメージがある場合、この補修を怠ると、塗装後に不具合が生じる原因となります。
まず、外壁にクラック(ひび割れ)がないかチェックします。
幅が細く、浅い小さなひびであれば、市販のコーキング材(シーリング材)をひびに充填し、ヘラで均して補修します。
乾燥後、表面をサンドペーパーで平滑にならしておきましょう。
外壁の継ぎ目部分(サイディングの目地など)のシーリングが劣化して、隙間が生じている場合も、増し打ちや打ち替えによる補修が必要です。
古いシーリングを剥がし、新しいシーリング材を充填してならします。
目地部分の補修は範囲が広く時間がかかりますが、雨漏りを防ぐために重要な工程です。
他にも、トタンや鉄部がある場合はケレン作業(サビ落とし)を行います。
金属ブラシや皮スキで、古い塗膜や錆をしっかり除去し、塗装面を整えておきます。
鉄部には、後で錆止め用の下塗り材(鉄部用プライマー)を塗ると安心です。
下地処理は地味で手間のかかる作業ですが、この工程を丁寧に行うかどうかで仕上がりと塗装の持ちが大きく変わります。
ひび割れや傷を放置したまま塗装しても、内部に雨水が侵入して建物を痛めてしまいます。
確実に補修を済ませてから、次の工程に進みましょう。
4. 養生(塗装しない部分の保護)

続いて、養生(ようじょう)作業です。
養生とは塗装しない部分をビニールシートやテープで覆って保護することを指します。
窓や玄関ドア、照明器具、雨樋、給湯器、エアコン室外機、植栽、駐車中の車など、塗料が付着してはいけないものは、全てビニールシートやマスキングテープで覆いましょう。
足場を組んでいる場合は、防護ネットで家全体を覆っているはずですが、それでも細かな塗料ミストが風で飛ぶ可能性があります。念には念を入れて養生してください。
「慎重に塗れば養生しなくても大丈夫では?」と思うかもしれませんが、養生を怠ると周囲を汚さないよう気を遣いすぎて、作業に集中できず、失敗する恐れもあります。
手間はかかりますが、塗らない部分の養生は決して手を抜かないようにしましょう。
養生が不十分だと、思わぬ所に塗料が飛んで汚してしまい、後で落とすのに苦労することになります。
特に、窓ガラスや車などは塗料が付くと取れにくいため、丁寧にシートで覆いテープで密閉しておきましょう。
5. 下塗り

いよいよ、塗装工程に入ります。
まずは、下塗り(したぬり)です。
下塗りとは、下地と仕上げ塗料の密着性を高めるために、最初に塗る塗料(下塗り材)を塗装する工程です。
下塗りには、壁の種類や状態に応じて適切な下塗り材を選びます。
一般的な外壁であれば、シーラーと呼ばれる、透明または白濁色の下塗り塗料を全面に塗ります。
シーラーは、外壁表面に染み込み、上塗り塗料との接着剤のような役割を果たします。
また、傷んだ外壁が上塗り塗料を過剰に吸い込むのを防ぐ効果もあります。
モルタル壁で、小さな凹凸やひび割れが多い場合は、粘度の高いフィラーという下塗り材を使って面を平滑に整えることもあります(ただしフィラーは扱いが難しくDIYには不向きです)。
金属部分には、錆止め効果のあるプライマーを下塗りとして塗っておく必要があります。
下塗り材を選んだら、ローラーで壁全面に均一に塗布します。
広い面は、中〜大型のローラーで手早く塗り、細かな隅や縁は刷毛で塗り残しのないように塗ります。
下塗り塗料は、サラッとしていて扱いやすいため、DIYでも比較的塗りやすい工程です。
下塗りをしっかり行うことで、この後に塗る上塗り塗料が壁にしっかり密着し、剥がれにくく長持ちする塗膜になります。
逆に下塗りを疎かにすると、仕上がり後、すぐに塗膜が剥離してしまう原因になりますので、ムラなく丁寧に塗りましょう。
下塗り塗装後は、塗料メーカーが指定する乾燥時間を守って十分に乾かします。
下塗りがしっかり乾いてから、次の工程に進んでください。
6. 中塗り・上塗り(仕上げ塗装を2回施工)

下塗りが完全に乾いたら、上塗り塗装を2回行います。
1回目の上塗りを「中塗り」、2回目を「上塗り(仕上げ塗り)」と呼びます。
使用する塗料は、中塗り・上塗りともに同じ仕上げ用塗料を使います。
なぜ、上塗りを2回も塗る必要があるのかというと、1回塗りではどうしても塗膜が薄くなり、耐久性が不足するためです。
外壁塗装は、基本的に、下塗り+中塗り+上塗りの三度塗りが基本であり、メーカーの塗料も規定の二度塗りで本来の性能が発揮されるよう設計されています(詳細はこちらの記事も参照)。
中塗りでは、まず壁面全体に希望の色の塗料を塗ります。
乾燥後、上塗りでもう一度、同じ塗料を重ね塗りすることで、塗膜に十分な厚みがつき、耐候性・耐久性が向上します。
また、二度塗りすれば塗り残しや色ムラもなくなり、美しく均一な仕上がりになります。
塗装方法は、通常はローラー塗装ですが、細かい部分は刷毛、模様付けや広範囲を短時間で仕上げたい場合は、スプレーガンによる吹き付け塗装を併用することもあります。
それぞれの塗装方法には長所短所があり、現場に応じて使い分けられます(塗装方法の違いについてはこちらの記事で詳しく解説しています)。
DIYでは一般的なローラー塗装をメインに、細部は刷毛で仕上げるとよいでしょう。
中塗り塗装後、再度、規定の乾燥時間を置いてから、上塗りに移ります。
上塗り(二回目の塗装)では、最終的なツヤや質感が決まります。
塗り残しがないよう、隅々まで丁寧に塗りましょう。
二度目の上塗りまで完了したら、塗装面全体をよく確認して、色ムラや塗り漏れがないかチェックします。
気になる箇所があれば、塗料が乾いてから、小さな刷毛でタッチアップ補修しておきます。
7. 養生撤去・足場解体と後片付け

塗装工程が、全て完了したら、養生材の撤去と足場の解体を行い、清掃して仕上げます。
ビニールシートや、マスキングテープで覆っていた箇所をゆっくり丁寧にはがします。
乾いた塗料が、付着した養生材は、剥がす際にパラパラと剥離片が落ちることがあるので注意しましょう。
全ての養生を外し終えたら、飛び散った塗料や、ゴミが残っていないか、敷地内を確認し、清掃します。
塗料の空き缶や、使い古した刷毛・ローラーなどの廃棄物も適切に処分しましょう。
塗料の残りは、フタをしっかり密閉して涼しい場所に保管し、捨てる場合は固化剤で固めるか、新聞紙などに染み込ませて乾燥させ、不燃・可燃ゴミの区分に従って処分してください(※自治体によって分別方法が異なるため、塗料廃棄は各市町村の指示に従ってください)。
最後に依頼していた足場業者に連絡し、足場を解体してもらいます。
足場解体の際も騒音や作業車の出入りがありますので、事前に近隣へ挨拶しておくと良いでしょう。
外壁塗装DIYで失敗しないためのポイント

初めてDIYで塗装する方が、陥りがちな失敗を防ぐため、以下に注意すべきポイントをまとめます。
事前にしっかり計画・確認し、焦らず丁寧に作業することで、仕上がりの品質と安全性を確保できます。
天候と気温を選ぶ
塗装作業は、天候に大きく左右されます。
塗装日は、雨が降らず、湿度が低めの晴天が望ましく、気温も、5℃以下や35℃以上の日は避け、15〜25℃程度の穏やかな陽気の日を選びましょう。
塗装後、しばらく雨が降らないことも確認し、数日間、好天が続く時期を狙って作業計画を立てます。
塗料の使用期限を守り、よく攪拌する
古い塗料や、開封後時間が経った塗料は、本来の性能を発揮できない恐れがあります。
購入した塗料の使用期限内に使い切りましょう。
また、缶を開ける前によく振り、中身を棒で底からしっかり混ぜて、塗料を均一な状態にしてから使用します。
特に、顔料が沈殿しやすい塗料は入念に攪拌(かくはん)してください。
塗りムラ・塗り残しに注意し丁寧に塗装する
広い壁面は、区画ごとに順序立てて塗り進め、「重ね塗り」の境目が乾かないうちに、周囲と馴染ませるように意識しましょう。
一度に広範囲を塗ろうとせず、一定のペースで、丁寧にローラーを転がすことでムラを防げます。
もし、塗り残しを発見した場合は、塗料が乾いてから、小さな刷毛で補修すると綺麗に仕上がります。
各工程で乾燥時間を厳守する
下塗り・中塗り・上塗りそれぞれで、塗料メーカー指定の乾燥時間をしっかり守りましょう。
焦って次の工程に進むと塗膜に不具合が生じます。
気温や湿度によって乾き方は変わるため、暑い日や寒い日には特に注意が必要です。
「少しベタつくけど次を塗ってしまおう」などという判断は禁物です。
高所作業は安全第一
2階部分や、屋根付近の塗装は、無理をしないことが肝心です。
安定した足場や、高さに合った脚立を用意し、作業時は、必ずフルハーネス型の安全帯を装着します。
ヘルメットと滑りにくい靴も着用して、安全を最優先に作業してください。
少しでも不安を感じたら、無理せず中断し、必要ならプロに任せる勇気も大切です。
近隣への配慮を忘れない
洗浄時の音や、塗装中のニオイ・塗料飛散など、ご近所への影響にも注意しましょう。
特に、油性塗料は、強い臭気が発生するため、事前に近隣宅へ「○日から外壁塗装を行います。塗料のニオイ等ご迷惑をおかけします」と一言挨拶しておきましょう
足場設置や解体の日程も知らせておくと、トラブル防止になります。
廃棄物を適切に処理する
作業後の後片付けも重要です。
使い終わった刷毛やローラーは、新聞紙などでできるだけ塗料を拭き取り、水性塗料なら水、油性塗料ならシンナーで洗浄します。
汚れた養生シートや、マスキングテープは回収し、乾いた塗料片とともにゴミ袋にまとめます。
余った塗料は、蓋をしっかり閉めて冷暗所に保管し、不要な場合は凝固剤で固めてから地域のルールに従って廃棄してください(不明な点は自治体の清掃部署に確認を)。
DIYとプロ施工の費用・時間の比較

ここで、DIYとプロ依頼での費用面や所要時間の違いについて、簡単に整理しておきましょう。
DIYで外壁塗装する場合の主な費用内訳は、塗料代・道具代・足場代です。
塗料代は、使用する塗料のグレードにもよりますが、一般的なシリコン塗料で30坪の家の場合15〜25万円ほど、道具類の購入に5万円前後、足場の設置費用に15〜20万円程度かかります。
人件費はゼロですが、これらを合計すると、DIYでもトータル30〜50万円程度は見込んでおく必要があります。
一方、プロの塗装業者に依頼した場合の費用相場は、30坪の戸建てで、おおよそ50〜150万円です。
これは、塗料代・足場代・人件費など全て込みの金額です。
DIYに比べると高額に感じるかもしれませんが、プロならではの高品質な仕上がりと長期間の耐久性が期待できます。
また、保証やアフターフォローが付く場合も多く、施工後の安心感も得られます。
時間の面でも大きな差があります。
プロは、チームで連日作業するため、約2週間で終わるところ、DIYでは一人で休日のみの作業だと数ヶ月〜半年以上かかることもあります。
作業に長期間を要すると、天候不順による中断リスクも高まり、その間ずっと足場や養生ネットを設置しておく必要があるため、近隣への負担も増えます。
また、長期的なコストパフォーマンスも考慮しましょう。
DIYは初期費用を安く抑えられても、もし、塗装の耐久性が低く、数年で塗り直しが必要になれば、結局プロに頼んだ場合より、高くつく可能性があります。
プロ施工なら、適切な下地処理と厚膜塗装で10年以上の耐久性が見込めるため、長い目で見れば割安になるケースも多いのです。
このように、費用・時間面では、DIYよりプロ施工が有利な点が多くあります。
DIYにこだわりすぎず、必要に応じて、専門業者の力を借りる柔軟さも大切です。
プロに依頼すべきケース(DIYが難しい場合)

最後に、「無理にDIYせず最初からプロに外壁塗装を任せた方が良いケース」について挙げておきます。
以下のような場合は、DIYでは対応が難しくリスクも高いため、最初から信頼できる塗装業者に依頼することを検討してください。
建物が高さのある(3階建て以上の)住宅の場合
高所での作業が多くなり、安全確保が非常に難しくなります。
プロは、高所作業の訓練を受け、多くの場合、資格も持っていますので、安全面を考えると、初めから任せる方が賢明です。
外壁に大規模な補修が必要な場合
外壁そのものに、深刻なひび割れや欠損、下地の腐食がある場合は、建物の構造にも関わる修繕が必要です。
プロなら、劣化状態を的確に診断し、適切な補修方法で対応できます。建物の安全性を確保するには専門的な技術が欠かせません。
特殊な塗装仕上げや技術を要する場合
意匠性の高い模様塗装や、特殊塗料を使用する塗装などは、高度な技術が必要です。
例えば、砂壁調の吹き付け模様を出したい場合や、海沿いで塩害に強い無機塗料を使う場合など、専門知識と技能を持つプロの腕が求められます。
工期に制約があり早く仕上げる必要がある場合
例えば、「今年中には引っ越ししたい」「台風シーズン前に終わらせたい」など、時間的猶予が少ない場合、プロに任せた方が、段取り良く、短期間で完成できます。
DIYだと、天候や作業ペース次第でいつ終わるか読めませんが、プロなら効率的な計画とチーム作業で迅速に仕上げてくれます。
施工後の保証やアフターフォローを重視する場合
専門業者に依頼すれば、通常工事後5〜10年程度の保証が付き、万が一、不具合があっても無償補修してもらえる安心感があります。
DIYでは、当然、そうした保証は得られません。
長期のメンテナンス計画まで考えるなら、プロに任せて保証を付けてもらう方が、結果的に安心・お得と言えるでしょう。
上記に当てはまる場合や、DIYに少しでも不安がある場合は、無理をせず、複数の塗装業者から見積もりを取り、納得のいく価格と内容で、依頼できる業者を選ぶことをおすすめします。
優良な業者であれば、こちらの要望や不安点もしっかり汲み取った上で、最適なプランを提案してくれるはずです。
記事のまとめ

外壁塗装をDIYで行うことについて、ポイントをおさらいしましょう。
DIY塗装は、費用を大きく抑えられるメリットがある一方で、高所作業の危険や仕上がり品質への不安など多くの課題があります。
実施する際は、足場の設置や下地処理・三度塗りの徹底など、プロ並みに慎重な準備と丁寧な施工が必要です。
今回、解説したように、DIYで施工する場合は、十分な時間と体力を確保し、道具類を万全に揃えて計画的に進めましょう。
特に安全対策と近隣への配慮は怠らないようにしてください。
一方で、「やはり自分でやるのは難しいかも…」と感じたら、無理せず信頼できる専門業者に依頼することをおすすめします。
できるだけ希望にあった業者を探したい場合、外壁塗装駆け込み寺にお申し込みいただければ、近隣の優良な外壁塗装業者を無料で紹介いたします。
DIYとプロ依頼、それぞれのメリット・デメリットを踏まえて、ご自身にとって最適な方法で大切なお住まいの外壁を美しくよみがえらせましょう。
外壁塗装は、適切に施工すれば、お住まいの寿命を延ばす重要なメンテナンスです。
費用や手間ばかりに目を向けず、安全と仕上がりを第一に考え、悔いのない選択をしてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。少しでも皆様の外壁塗装計画のお役に立てれば幸いです。