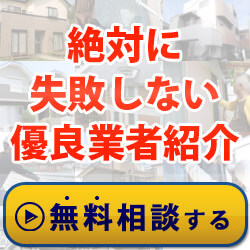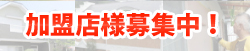外壁塗装を行う際には、実にさまざまな道具・工具が必要です。
万能な道具は存在せず、プロの業者であっても、DIYであっても、工程ごとに適切な道具を使い分けることが重要になります。
例えば、塗料を塗る作業にはローラーや刷毛(はけ)、スプレーガンなどの塗装道具を使用しますし、古い塗膜を落とす下地処理には、皮スキやサンドペーパーといった下地処理用の道具が欠かせません。
また、塗装しない部分を保護する養生(ようじょう)には、マスキングテープやビニールシートといった養生用の道具を用います。
中には、業務用の高圧洗浄機や仮設足場など、高価で個人では入手しづらい専門機材もあります。
こうした道具を上手に活用することで、安全で効率的に高品質な外壁塗装を実現できるのです。
この記事では、外壁塗装で使用される代表的な道具の種類を工程別に詳しく解説します。
一般の施主様やDIY初心者の方にも分かるよう、専門用語は丁寧に説明しながら進めます。
塗料(ペンキ)そのものの種類や選び方については本記事では扱いませんので、興味のある方はこちらの塗料の種類に関する記事もご参照ください。
洗浄工程で使用する道具

塗装の最初の工程は、外壁の洗浄作業です。
塗装面の汚れや、古い塗膜をきれいに落とすことで、新しい塗料がしっかり密着し長持ちします。
そのために使われる代表的な道具を紹介します。
高圧洗浄機

高圧洗浄機は、強力な水圧で壁面の汚れを洗い流すための道具です 。
プロの現場では、エンジン式などの業務用高圧洗浄機が使われます。
その水圧は、家庭用(電気式)の機種よりもはるかに高く、15MPa(メガパスカル)以上の圧力で洗浄できるものもあります。
この高圧水流により、頑固なホコリやコケ・カビ、古い塗膜の一部までも洗い落とすことができます。
しっかり洗浄することで、後から塗る塗料の密着が良くなり、仕上がりの耐久性も高まります。
ただし、業務用の高圧洗浄機は、購入費用が高額で、一般の方が一度のDIY塗装のためだけに揃えるのは現実的ではありません。
DIYの場合は、家庭用の電気式高圧洗浄機(比較的安価)を使用したり、必要に応じて業務用の機種をレンタルする方法もあります。
外壁と屋根の洗浄だけ業者に依頼するという選択肢も有効です。
また、高圧洗浄時には、水しぶきが飛び散るため、後述する養生シートやメッシュシートで周囲を覆っておくことも大切です。
バケツ・ブラシ・外壁用洗剤

洗浄箇所が手の届く範囲で、汚れが比較的軽度な場合や、高圧洗浄機が用意できない場合には、バケツとブラシによる手洗いで外壁を清掃することも可能です。
外壁用の洗浄剤(バイオ洗浄液など)をバケツの水に希釈し、ブラシで壁面をこすって汚れを落としていきます。
家庭用のデッキブラシやスポンジブラシでも代用できますが、外壁材を傷めない柔らかめのブラシを選ぶと良いでしょう。
高圧洗浄に比べると手間はかかりますが、水道と最低限の道具だけでできる手法です。
洗剤はホームセンターで「外壁洗浄用」「カビ取り用」などの製品が市販されています。
洗浄後は、洗剤成分が残らないよう十分にすすぎ、水分をしっかり乾燥させてから次の工程に進みます。
高圧洗浄機ほどの洗浄力はありませんが、小規模な塗装や部分補修程度であれば手作業洗いでも対応可能です。
下地処理に使う道具(ケレン作業など)

洗浄後、塗装前に行うのが下地処理です。
既存の塗膜が剥がれかけている部分やサビ・汚れが残っている部分を取り除き、塗装面を滑らかに整える工程を一般にケレン作業と呼びます。
ケレンを丁寧に行うかどうかで塗装の持ちが大きく変わるため、「外壁塗装はケレン作業が命」と言われるほど重要です。
ケレン作業に使用される代表的な道具を紹介します(ケレンの目的や重要性については、ケレン作業の解説記事も参考にしてください)。
サンドペーパー・ワイヤーブラシ等の研磨道具

サンドペーパー(紙やすり)や研磨パッド類(工業用たわしのマジックロンなど)、金属製のワイヤーブラシは、細かな部分の古い塗膜やサビを手作業で落とすための基本的な道具です。
塗装面をゴシゴシと擦り、表面のザラつきや浮いた塗膜を除去したり、逆に表面をわずかに傷つけて(これを「目荒し」「足付け」と言います)塗料の食いつきを良くする目的でも使われます。
紙やすりには、目の粗さ(番手)があり、#60~#120程度の粗めを使って古い塗膜を削り落とし、#180~#400程度の細かいもので、表面を滑らかに仕上げるといった使い分けをします。
ワイヤーブラシは、金属部分のサビ落としに有効です。
ただし、手作業では広範囲を処理するのに限界があるため、大面積のケレンには後述する電動工具も併用します。
電動サンダー(研磨機)

電動サンダー(電動研磨機)は、広い面積の塗膜を効率よく、研磨・剥離するのに用いられる電動工具です 。
手持ち式で、平らなヤスリ面が、高速振動または回転し、壁面に当てることで、古い塗料やサビを削り落とします。
大きな外壁面や、フェンス・鉄部など、手作業では大変なケレン作業も、電動サンダーがあれば、短時間で均一に処理できます。
DIYで一度きりの塗装作業のために、高価なサンダーを購入するのは負担ですが、必要に応じて工具レンタルを利用することも可能です。
電動サンダーを使用する際は、粉塵が大量に発生するため、防塵マスクや保護メガネを必ず着用してください。
また、周囲に粉塵が飛び散らないよう養生シートで覆うなどの配慮も必要です。
皮スキ・スクレーパー(ヘラ状の削り道具)

皮スキ(皮剥き)やスクレーパーと呼ばれるヘラ状の道具も、下地処理の現場で活躍します。
木べらや金属製ヘラの先端を使い、浮いてしまった古い塗膜や錆の塊などを削り取るために用います。
細かな部分や角ばった部分など、サンドペーパーだけでは落としきれない塗膜をこそげ落とすのに適しています。
皮スキは、特に金属部のサビ取りや、木部の古い塗膜剥がしに使われます。
先端が鋭利なので、塗装面を傷つけすぎないよう注意が必要ですが、大きくめくれている塗膜やペリペリと剥がれる塗料を効率よく除去できます。
スクレーパーにも、幅広タイプや先の尖ったタイプなど、様々な形状があり、状況に応じて使い分けます。
コーキング材・コーキングガン(シーリング道具)

モルタル外壁のひび割れ補修や、サイディングボードの継ぎ目シーリング補充などには、コーキング材(シリコンシーラントなどの充填剤)とコーキングガンが必要です。
一般的なカートリッジ式のコーキング材を、コーキングガン(コーキング用の専用押出し工具)にセットし、トリガーを引くと、先端からペースト状のシーリング材が押し出されます。
外壁塗装のタイミングでは、経年で劣化した古いシーリング材を一度すべて剥がし、新しいコーキング材を充填し直すのが一般的です。
充填後は、ヘラで表面を平滑にならし(これも広義では下地処理の一環です)、乾燥硬化させてから塗装します。
コーキング材は上から塗装可能な外壁用のものを選ぶ必要があります。
DIYでも市販のコーキングガンとシーリング材で小さな隙間程度なら補修できますが、大規模なシーリング打ち替えは技術を要するため、必要に応じてプロに依頼すると安心です。
コーキングに関しては、こちらの記事にも詳しく解説しています。
養生に使う道具(塗装箇所以外の保護)

塗装作業に入る前に、塗料を塗らない部分を保護する養生(ようじょう)作業が欠かせません。
養生とは、塗料の飛散や塗りムラが他の箇所につかないように覆い隠すことです。
しっかり養生することで。「塗料が窓ガラスについてしまった」「隣家の車に塗料ミストが飛んでトラブルに…」といった事故も未然に防げます。
ここでは養生に使われる代表的な道具類を紹介します。
マスキングテープ

マスキングテープは、塗装しない部分との境目に貼って塗料のはみ出しを防ぐためのテープです。
幅や材質にいくつか種類がありますが、一般的には塗装用の和紙テープが使われます。
例えば、窓枠やドア枠と外壁の境界線、コンセントカバーや配管など細かな部分の縁取りに貼り付けて、刷毛やローラーの塗料が付着しないようにします。
マスキングテープは、手でまっすぐ簡単に切れること、剥がしたときに糊残りしにくいことが特長です。
一時的に貼って塗装後には綺麗に剥がせるので、塗装現場では欠かせないアイテムとなっています。
ホームセンターで安価に購入でき、色も目立つ黄色や青色などが多いため、作業箇所が分かりやすい利点もあります。
養生シート・マスカー

養生シートは、ビニール製の薄いシートで、塗装しない部分の広い範囲を覆うために使います。
建物の床や壁、植木、窓ガラス、玄関ドアなど、飛び散る塗料ミストやホコリから保護したい箇所をシートで覆っていきます。
シートの端を先述のマスキングテープで固定して密閉することで、隙間から塗料が入り込むのを防ぎます。
マスカーは、この養生シートとテープが一体化した便利な道具です。
ロール状になったテープにビニールシートが折りたたまれて付属しており、テープを貼ってからシートを広げるだけで簡単に覆うことができます。
窓や床面の養生をスピーディーに行えるため、プロの現場でも頻繁に使われます。
ブルーシート(床養生用)

ブルーシートは青色の厚手のシートで、主に地面や庭先を広範囲に覆うのに使われます。
外壁塗装では、建物の外周に足場を組み、その下に地面養生としてブルーシートを敷きます。
これは、塗料が飛んで地面を汚したり、洗浄水や剥がれた塗片が散乱するのを防ぐためです。
ブルーシートは、防水性が高く丈夫なので、塗装期間中ずっと敷きっぱなしにしておいても破れにくく安心です。
敷地の広さに応じてサイズを選び、必要なら複数枚をガムテープなどで繋いで隙間なく覆います。
特に足場を立てる場合は、足場全体にメッシュの飛散防止ネット(下記参照)を張りますが、地面への養生としてもブルーシート併用が基本です。
養生カバー(自動車・植木用カバーなど)

移動が難しい物や塗料飛散で汚したくない大型物には専用の養生カバーを使います。
例えば、敷地内に駐車しているお車やオートバイには車両用の大型ビニールカバーをかぶせ、植木や植栽には植木用の専用カバーで覆います。
建物に隣接していて動かせない物ほど念入りにカバーリングしておくと安心です。
特に、近隣の住宅の車が近い場合などは、施工業者にお願いしてそちらにも養生カバーをかけてもらう配慮が必要でしょう。
万一、塗料ミストが飛んで他人の所有物を汚してしまうと大きなトラブルになりますので、塗装前の養生段階で防げるリスクは徹底的に対策します。
こうしたカバー類もホームセンター等で購入できますが、DIYの場合は使い捨てになることも多いため、安価な汎用ビニールシートで代用するケースもあります。
塗装に使う道具(塗り方別)

いよいよ塗料を塗る工程で活躍するのが塗装用の道具です。
外壁塗装の現場では、広い面積はローラーで塗り、ローラーで塗りにくい細部は刷毛で塗るという方法が一般的です。
また、模様付けや特殊な仕上げには、スプレーガンを用いた吹き付け塗装が行われることもあります。
それぞれの道具の特徴や種類を見ていきましょう。
ローラー(各種ローラーと関連道具)

塗装用ローラーは、毛のついた回転ローラーで、塗料を広範囲にムラなく塗れる道具です。
外壁塗装全体の作業の中でも、約8割を占める主力道具で、今や刷毛よりローラー塗りが主流になっています。
ローラーは、大きく分けてウールローラー(羊毛ローラー)と砂骨ローラーの2種類がよく使われます。
ウールローラーは、羊毛のように柔らかな繊維でできたローラーで、塗料含みが良く伸びも良いため、均一できれいな仕上がりになります。
毛足(毛の長さ)に短毛・中毛・長毛の種類があり、短毛は平滑な面を滑らかに塗るのに適し、長毛は壁の多少の凹凸も一度で塗れるため模様付き壁面に向いています。
中毛ローラーは、汎用性が高く、一般的な外壁で最もよく使われる標準サイズです。
砂骨ローラー(さこつローラー)は、内部がスポンジ状で多孔質になっており、一度に大量の塗料を含ませられるローラーです。
ドロッとした粘度の高い塗料や、厚塗り仕上げをする際に活躍し、塗料を厚く塗ることで独特のザラザラした模様(砂骨模様)を付けることもできます。
ウールローラーと砂骨ローラーは目的に応じて使い分けられており、最近では模様を付けるためのパターンローラーや、気泡を抜くための脱泡ローラーなど、特殊用途のローラーも存在します。
ローラーを使う際には、ローラーを差し込んで使う取っ手部分のローラーハンドルと、塗料を入れておくバケツである下げ缶(さげかん)も用意します。
一般的な建築塗装では、持ちやすく小回りの利くスモールサイズのローラーとショートハンドルの組み合わせが使いやすいです。
柄の長いロングハンドルは、高所や奥行きのある部分を塗れる利点がありますが、初心者には均一に力をかけるのが難しいため、扱いに注意が必要です。
なお、ローラーのサイズ(太さ・長さ)はレギュラー、ミドル、スモール、ミニスモールといった種類に分かれ、日本の住宅塗装ではスモールローラーが主流です。
素材も羊毛以外にナイロン製ローラーなどがあり、水性塗料に適したものや、模様を出さない滑らかな仕上げが得意なものもあります。
塗装箇所や使用する塗料に応じて最適なローラーを選ぶことが、仕上がりに直結すると言えるでしょう。
刷毛(はけ)

刷毛(はけ)は、細かな部分の塗装に欠かせない昔ながらの塗装道具です。
ローラーでは塗りにくい隅や角、細部を塗るのに用います。
刷毛だけでも非常に多くの種類がありますが、代表的なものを挙げると以下のようになります。
- 平刷毛(ひらばけ):毛先が平らな最もオーソドックスな刷毛。一度に塗れる幅が広いので、手すりや細長い板、広めの面などに適します。ベタ刷毛とも呼ばれ、昔はこの平刷毛で壁一面を塗装していましたが、現在では広面積はローラー塗装に取って代わられています。
- 筋交い刷毛(すじかいばけ):持ち手から毛先が斜め45度程度に曲がって植えられた形状の刷毛。日本独特の形状で、コーナーや隅、細い溝などを非常に塗りやすいため重宝します。
- 寸胴刷毛(ずんどうばけ):毛先が丸みを帯びて膨らんだ形状の刷毛。毛量が多く塗料の含みが良いため、一度にたっぷり塗料を含ませて塗れます。粘度の高い塗料(油性塗料や高粘度の下塗り材)を塗る際に適した刷毛です。
- 目地刷毛(めじばけ):先端が細く、小さな刷毛。サイディングの目地(ボードの継ぎ目)や細い溝を塗るための専用刷毛で、幅数ミリ程度の毛幅のものもあります。
- 隅切り刷毛:その名の通り隅(端部)を塗るための刷毛。先端が極細になっており、窓枠の縁や配管の裏など細かい補修塗りに使われます。ダメ込み刷毛とも呼ばれ、縁を「切る」用途に特化しています。
この他にも、塗装以外に掃除用途で使うラスター(ダスター)刷毛や、鉄部塗装用の鉄骨刷毛、水性塗料専用の化学繊維刷毛など多種多様な刷毛があります。
職人はこれらの中から塗料や塗る場所に応じて最適な一本を選び取って使い分けています。
毛の素材にも注目すると、伝統的には馬毛・豚毛・ヤギ毛などの獣毛が多く使われますが、水性塗料を扱う際は固まりにくいナイロン等の化学繊維製の刷毛(「水性刷毛」)が便利です。
スプレーガン(吹き付け塗装用機材)

スプレーガンは、塗料を霧状に噴射して塗装面に吹き付けるための道具です。
ピストルのような形状をしており、引き金を引くと先端ノズルから塗料のミスト(霧)が勢いよく噴き出します。
広い面積を非常に短時間で塗装できるため、かつては外壁塗装でも広く用いられていました。
現在でも、モルタル外壁に凹凸模様をつける「リシン吹き付け」や、「スタッコ(ざらざら模様)」仕上げなど特殊な意匠には専用のスプレーガンが使われています。
スプレーガンには、方式の違いによりエアスプレーとエアレススプレーの2種類があります。
エアスプレーはコンプレッサーで圧縮した空気を使い、その空気の流れに塗料を乗せて霧化(ミスト状)させる方式です。
圧縮空気式とも呼ばれ、重力式・吸上げ式・圧送式など塗料カップの位置や供給方法によってさらに種類が分かれます。
一方、エアレススプレーは空気を使わずに、塗料そのものに高圧をかけてノズルから噴射する方式です。
空気を混ぜない分だけ一度に大量の塗料を噴出でき、粘度の高い塗料でも安定して噴射できるというメリットがあります。
また、エアレスの方が霧の拡散が少なく塗料の無駄が減る利点もあります。
ただし、スプレー塗装にはいくつかデメリットもあります。
塗料が微粒子になって周囲に飛散しやすいため、養生を非常に広範囲に厳重に行わなくてはなりません。
また、コンプレッサーの作動音や霧吹きの音が大きく、シンナー臭も発生しやすいため、住宅街ではご近所への配慮が必要です。
加えて、ムラなく吹き付けるには熟練した技術が求められるため、DIYでのスプレーガン使用はあまり推奨されません。
現在の一般的な戸建て塗装では、ローラーと刷毛による手塗りが主流であり、スプレーガンは特殊な場合に限られると言えるでしょう。
ヘラ・コテ(塗装模様付け用の道具)

左官職人が用いるコテや、先端の平たいヘラも広義には塗装関連の道具に含まれます。
例えば、厚めに塗った塗材をコテで、拭き取るようにならして独特の模様を出す「こて押さえ仕上げ」や、砂壁調仕上げの際にコテでパターンを描くケースです。
DIYでコテを使う場面としては、ひび割れ補修に充填剤やモルタルをコテで埋め込んだり平らにならしたりする作業が考えられます。
ヘラについても、コーキング充填後のならし作業や、ペンキ缶のフタ開け・攪拌など細かな用途で出番があります。
ヘラ・コテ類は木製・金属製・樹脂製など素材も様々です。
なお「ケレン」という言葉は上述のように、下地調整全般を指しますが、狭義には皮スキやスクレーパーでの手作業剥離のことを指しますので、ヘラ・コテとは区別して考えてください。
その他の必要な道具・備品

前項までは、塗装作業の各工程ごとに使用する主な道具を紹介しましたが、それ以外にも安全作業や作業効率のために用意しておきたい道具・備品があります。
脚立・足場

2階以上の高所の外壁を塗るには、足場の設置が基本です。
ただし、DIYで平屋部分を少し塗る程度であれば脚立でも作業自体は可能でしょう。
脚立は移動や設置が手軽ですが、高所での姿勢が不安定になりやすく、塗装できる範囲も狭いため効率が悪くなります。
一方、足場を組めば建物周囲に安定した作業スペースが確保され、手元・足元がぐらつかないので安全かつ丁寧な作業ができます。
さらに足場には塗料飛散防止用のメッシュシートを張ることができるため、周辺環境への影響も軽減できます。
一般の方が自力で足場を組むのは危険が伴うため現実的ではありません。
必要な場合は、足場専門業者に依頼して組んでもらうか、無足場工法(ブランコ作業など特殊高所作業)を検討することになります。
ただ、無足場工法も高度な安全対策が必要なため、基本的には戸建て塗装では足場設置が前提です。
足場のレンタル費用は、建物規模によりますが決して安くないため、DIYで高所全面を塗り替えるのはコスト面・安全面からもハードルが高いと言えます。
足場の重要性や費用感について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
ヘルメット・保護メガネ・マスク・手袋などの安全保護具

外壁塗装作業では、安全対策も非常に重要です。
特に、脚立や足場を使った高所作業では、必ずヘルメットを着用しましょう。
高い所から万一転落した際に命を守る最後の砦になります。
また、塗料が飛び散ったりサンダーの粉塵が舞ったりしますので、保護メガネや防塵マスクで目や呼吸器を守ることも必要です。
塗料には、有機溶剤(シンナー)を含むものもあるため、防毒マスクを使うケースもあります。
服装は汚れても良い作業着を着用します。
袖口や裾がだぶつかない動きやすい服装が望ましいです。
塗料は、飛沫が衣服に付くとなかなか落ちないため、専用つなぎやポリ製の使い捨て防護服を着る職人もいます。
靴は、滑りにくくつま先の保護された安全靴か運動靴で、決してサンダルや踵の高い靴で作業しないでください。
長靴は一見良さそうですが、重く動きづらいため塗装作業には不向きです。
加えて、塗料缶を開封する缶切り(ペンキ缶オープナー)や、塗料をよく攪拌する撹拌棒(かくはんぼう)、塗料を入れるカラーバケツなど、小物類も用意しておくとスムーズに作業できます。
まとめ

外壁塗装に必要な道具類を、洗浄・下地処理・養生・塗装・安全対策の各段階に分けて詳しく見てきました。
使用する道具の種類は多岐にわたりますが、それぞれに役割があり、適材適所に使い分けることで塗装作業の品質と効率が飛躍的に向上します。
ローラー・刷毛・スプレーガンといった塗装方法の違いによって、仕上がりの風合いも異なりますし、下地処理を丁寧にするかどうかで塗膜の寿命も大きく変わります。ど
の道具が優れているということではなく、外壁の状態や塗料の性質に合わせて最適な道具を選ぶことが重要だと言えるでしょう。
DIYで外壁塗装に挑戦する場合は、ここで挙げた道具の中から必要なものを揃える必要があります。
高圧洗浄機や足場など個人では用意しづらいものは、レンタルや部分的な業者依頼も検討しましょう。
道具を一通り買い揃える費用や労力を考えると、場合によっては最初からプロに任せた方が結果的に安く安全に済むこともあります。
DIYか業者依頼かを判断する際には、道具の準備や管理、作業の難易度もしっかり考慮してください。
外壁塗装に必要な道具の種類と特徴を理解することで、塗装工程への理解も深まったかと思います。
適切な道具を使い、正しい手順で施工すれば、美観を保ち建物を長持ちさせる高品質な塗装が可能です。
ぜひ本記事をお役立ていただき、安全第一で外壁塗装作業に取り組んでみてください。