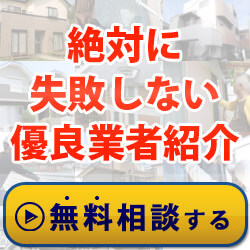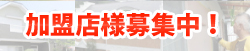木造住宅の外壁は、美しい木目や温かみのある外観が魅力ですが、他の外壁素材と比べて、定期的なメンテナンスが欠かせません。
木は、湿気や日射の影響を受けやすく、塗装せず放置すると、腐食やシロアリなどの被害を受け、建物の寿命を縮めてしまいます。
そのため、木造の外壁を長持ちさせるには、適切な塗装による保護が必要です。
本記事では、木造住宅の外壁塗装について、特徴や劣化症状、使用する塗料の選び方や塗装方法、費用相場、そしてDIYとプロどちらに依頼すべきかといった注意点まで詳しく解説します。
木造ならではのポイントを押さえて、後悔のない外壁塗装計画を立てましょう。
木造住宅ではなく、建物の木部の塗装に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。
目次
木造住宅の外壁の特徴と塗装が必要な理由

木造住宅では、外壁に天然の木材を使用することで得られる独特の風合いや温かみが大きな魅力です。
代表的な木造外壁材には、スギやヒノキなどの無垢板材のほか、板を加工して作る羽目板や下見板、さらに木片を接着剤で固めたパーチクルボード、木の繊維を成形したMDFなどがあります。
木材は、調湿機能があり、室内を快適に保つ効果や、自然素材ならではの癒やしを与えてくれますが、一方で、他の外壁材にないデメリットも抱えています。
最大の弱点は水分や湿気に弱いことです。
高温多湿の環境では、木材は腐りやすく、塗装などで保護しなければ、雨水を吸って傷みが急速に進行します。
また、木材はシロアリなどの害虫のエサにもなりやすく、未塗装の木部は虫が入り込み構造を脆くする恐れがあります。
さらに、紫外線によって木材は変色しやすく、直射日光にさらされる部分は、数年で色あせや黒ずみが目立って外観が損なわれてしまいます。
このように、木造外壁は、雨・湿気・虫・日光といった自然環境の影響を強く受けるため、何もせず放置すると、美観が損なわれるだけでなく、構造自体の劣化につながります。
そこで重要になるのが、外壁塗装です。
木材専用の塗料で塗装することで、木部表面に防水性・防腐性・防虫性・耐紫外線性を持たせ、木造外壁を長持ちさせることができます。
実際、木材用塗料には防腐剤や防蟻剤(防シロアリ)、防虫剤、紫外線吸収剤などが配合された製品が多く、塗装することで木を腐敗や害虫から守る効果が期待できます。
ただし、木は生きていた素材ゆえに、伸縮(膨張・収縮)を繰り返すという特徴もあります。
そのため、コンクリートや金属の外壁に比べ、木部の塗装膜は、動きに追随できず、剥がれやすい傾向があります。
耐久性が10年程度とされる塗料を塗っても、木部の場合は、3~5年ほどで保護効果が落ちてしまうケースもあるほどです。
つまり、塗装しても劣化が早いのが木造外壁の宿命であり、裏を返せば、こまめな塗り替えが必要になる建材だと言えます。
このような理由から、木造住宅の外壁を美しく安全な状態に保つには、定期的な塗装メンテナンスが欠かせません。
適切な塗装によって、木材の魅力を活かしつつ、雨風や紫外線から家を守り、ひいては、建物全体の寿命を延ばすことにつながります。
逆に塗装を怠ると、木部が深刻に傷んでしまい、外壁材そのものの張り替えという大掛かりな修繕が必要になる恐れもあります。
塗装は、張り替えに比べ、費用もずっと安く済みますので、大切なマイホームを守るためにも、木造外壁は、早め早めの塗装を心がけましょう。
木造外壁の劣化症状と塗り替え時期の目安

木造住宅にお住まいの場合、次のような劣化症状が見られたら、外壁の塗り替え時期です。
- 色あせ・変色:塗装した当初の色が薄くなり、木部が全体的に退色している。紫外線による日焼けや雨染みにより、部分的にまだらな変色が起きている。
- チョーキング現象:外壁を手で触ると白い粉状のものが手につく。塗膜の樹脂が劣化して顔料が表面に粉吹きしている状態で、塗装の防水効果が失われ始めたサイン。
- 塗膜の剥がれ:塗装がペリペリと剥離し、木材が露出している部分がある。初期段階では塗膜のふくれ(水泡状の膨れ)として現れ、進行すると剥がれて下地が見える。
- ひび割れ・反り:木製の外壁板に細かなクラック(割れ目)や、板材の反り・浮きが生じている。乾燥や湿気の影響で木材自体が痩せたり変形した可能性がある。
- カビ・藻の発生:外壁表面が黒ずんでいたり、緑色の藻が付着している。塗膜の防水性が落ち、木材に水分が染み込んで栄養源となり微生物が繁殖している。
- シロアリの兆候:羽アリを見かけたり、木部に無数の小穴や木屑が見られる場合は要注意。塗装が劣化した木材は害虫にとって侵入しやすい状態になり、白アリ被害が進行する恐れがあります。
- コーキングの割れ:外壁の継ぎ目(目地)に充填されているシーリング材が硬化して割れている。隙間から雨水が侵入しやすくなり、木下地を腐らせる原因になります。
以上のような劣化症状は、塗装の防護性能が低下し、外壁材が外気や水分にさらされていることを示しています。
このまま放置すると、雨水が染み込んで、木材内部で腐食が進んだり、前述のとおり、害虫が入り込んで構造体まで食われてしまう危険性が高まります。
幸い、劣化の初期段階であれば、塗り替えによって、木材の損傷拡大を防ぐことが可能です。
木造外壁の再塗装時期は、一般的に、前回塗装から5〜6年程度が目安とされています。
他の外壁材では、10年が塗り替えの目安と言われますが、木部は先述のとおり、塗膜の劣化が早いため、早めのサイクルで塗り替える方が安全です。
特に、南向きなど日差しが強い面や、雨風の影響を受けやすい面は、劣化が早く進みますので、3〜5年程度で状態をよく点検して、必要なら塗り替えを検討しましょう。
もちろん、塗料の種類や家の立地環境によって前後しますが、定期点検と早めのメンテナンスが、木造住宅を長持ちさせるコツです。
もし、築年数が長く(例えば築40~50年)一度も外壁のメンテナンスをしていないような場合は、まず、専門業者による診断を受けることをおすすめします。
木材の劣化が激しい場合、塗装だけでは対処しきれず、外壁板の張り替えが必要になるケースもあります。
逆に、骨組みや外壁材が健全な状態であれば、古い木造住宅でも、塗装による再生は十分可能です。
なお、外壁塗装が必要な典型的な劣化サインについては、こちらの記事も参照してください。
劣化症状に早めに気づき、塗装で対処しておけば、大掛かりな補修工事を防ぎコストの節約にもつながります。
木造住宅の外壁の塗装に適した塗料と選び方

木造住宅の外壁を塗り替える際には、使う塗料選びが極めて重要です。
モルタル壁やサイディング壁用の塗料ではなく、必ず木部に使える塗料を選ぶ必要があります。
塗料には、用途に応じて「木部用」「鉄部用」「コンクリート用」などと表示されていますので、外壁に木材が使われている場合は、木部用と明記された製品を使いましょう。
さらに木部塗装には、屋内用ではなく屋外(外部)用の塗料を選ぶことも大切です。
室内木部用のニスやペンキは屋外の過酷な環境に耐えられず、すぐに劣化してしまいます。
その上で、木造外壁に適した塗料には大きく分けて2種類のタイプがあります。
造膜型塗料(ペンキタイプ)の特徴

造膜型塗料とは、木材表面に塗膜(皮膜)を作って覆うタイプの塗料です。
一般的に「ペンキ塗り」と言われる塗装は、この造膜型で、下塗り(下地用)塗料と上塗り(仕上げ用)塗料を組み合わせて使用します。
木造外壁でも、モルタルやサイディングと同様に下塗り材+上塗り材で塗装するケースが多く見られます。
下塗り材(シーラーやプライマー)は、木部に塗料が染み込みすぎるのを防ぎ、かつ、上塗り塗料との付着を良くする役割があります。
上塗り材は、木材と下塗り膜を保護し、さらに色やツヤを与えて外観を美しく仕上げます。
造膜型塗料には、アクリル・ウレタン・シリコン・フッ素など様々な樹脂を主成分とした製品がありますが、木部用であれば基本的にどの樹脂タイプでも使用可能です。
ただし、前述のように木材は伸縮するため、造膜型の場合は、塗膜が剥がれやすい点に注意が必要です。
特に、高耐久で硬い塗膜を作るシリコン塗料やフッ素塗料でも、木の動きには追従できず、数年でひび割れや剥離を起こすことがあります。
一方、ウレタン塗料は、耐久年数こそ短めですが、柔軟性が高いため、木部への塗装に適していると言われます。
木造外壁を塗り替える際は、単に耐久年数が長い塗料を選ぶだけでなく、塗膜の柔軟さや過去の塗装履歴も考慮すると良いでしょう。
なお、既に木部に透明なクリア塗装やステイン仕上げがされている場合、その上から造膜型の不透明塗料を塗ると、十分に密着せず不具合が生じる恐れがあります。
過去にステイン系で塗装していた木部をペンキで塗り直す際には、旧塗膜を、しっかりサンディングで落とす、もしくは下塗りに専用の密着プライマーを使用するといった対策が必要です。
心配な場合は業者に相談し、適切な下地処理を施してもらいましょう。
浸透型塗料(ステインタイプ)の特徴

木造外壁ならではの塗料に浸透型塗料があります。
一般に「ステイン」と呼ばれる塗料で、木材の内部に染み込んで保護するタイプです。
このステイン系塗料を塗布すると、塗料成分が木材表面にとどまらず、繊維の内部まで浸透していきます。
表面に膜を作らないため、木材が伸縮しても、塗膜が割れたり、剥がれたりしにくいという利点があります。
また、木目を塗りつぶさずに、木の風合いを活かせるため、「自然な木の質感を残したい」という場合に適した塗装方法です。
一方で、ステイン仕上げは、造膜型のような厚い保護膜を作らない分、耐水性や耐久性は劣る点に注意が必要です。
塗装後のツヤも出せないため、光沢のある仕上がりにはなりません。
ステイン系塗料で外壁を塗る場合は、基本的に、下塗りから上塗りまで全てステインで行います。
木材が塗料をどんどん吸い込むため、何度か重ね塗りして色を濃くし、最後に保護目的のクリア塗料を上塗りして仕上げるケースもあります。
なお、ステイン塗装した木部は、色が薄くなってきたら、再度、同じ塗料を上から塗り重ねることでメンテナンスできます。
古い塗膜を完全に剥がす必要がないため、造膜型に比べて再塗装が容易というメリットもあります。
ただし、紫外線や雨で色落ちしやすいため、外観を美しく保つにはやはり数年おきに塗り直しが必要です。
木部塗料選びのポイント

最後に、木造外壁の塗料を選ぶ際に押さえておきたいポイントをまとめます。
- 必ず木部用・屋外用の塗料を使う:前述の通り、木材には木材専用の塗料を使用します。室内用ではなく耐候性のある屋外用を選びましょう。
- 防腐・防蟻・UVカット効果に注目:木材を守る塗料には、防腐剤や防蟻剤(シロアリ忌避)、防カビ剤などが配合されています。特に湿気の多い地域では、防腐・防カビ性能、シロアリ被害が心配な場合は、防蟻成分入りの塗料を選ぶと安心です。また、日当たりが強い面には、UVカット効果のある塗料が有効です。
- 下塗り材と上塗り材の相性:塗料によっては、下塗り(シーラー)が水性、上塗りが油性の組み合わせなど、相性が悪いと密着不良を起こす場合があります。基本的には、メーカー推奨の組み合わせを守り、水性には水性、油性には油性で統一するのが安全です。
- 木目を活かすか隠すか方針を決める:塗装後の仕上がりイメージを明確にしましょう。木の質感を残したいなら、ステイン系、外壁の色をガラリと変えてイメージチェンジしたいなら、造膜系の不透明塗料を選びます。一度不透明塗装してしまうと木目を復元するのは困難なので、塗装前によく検討してください。
- 高耐久塗料よりも柔軟性を重視:木部に15年耐久の高級塗料を塗っても、木の動きで3~5年ほどで劣化してしまっては意味がありません。それよりも適度な価格で弾力のある塗料を選んだ方がコストパフォーマンスに優れる場合があります。塗料カタログの「伸び率」や「ひび割れに対する追随性」といった項目も確認すると良いでしょう。
- 既存塗膜との相性を考慮:前回までにステイン仕上げだった木部に造膜塗料を塗る、あるいはその逆など、異なる種類の塗料を重ねる場合は注意が必要です。状況によっては古い塗膜を完全に除去する下地処理が要ります。可能であれば前回と同じ種類の塗料で塗り替えるのが無難です。
以上を踏まえ、迷ったときはプロの塗装業者に相談してみましょう。
塗料メーカーの製品カタログや業者の提案を参考に、自宅の木造外壁に最適な塗料を選定することが大切です。
木造外壁塗装の施工手順とポイント

木造外壁の塗装工事は、ただペンキを塗れば良いというものではなく、適切な手順を踏む必要があります。
ここでは、一般的な外壁塗装の流れと、木部ならではの注意点について説明します。
1. 下地処理(洗浄・ケレン)

古い木造外壁を塗り替える際、まずは、下地処理として汚れ落としと素地調整を行います。
屋外に晒された木の外壁は、長年の埃やカビで汚れが蓄積し、さらに表面がざらざらと毛羽立っていることが多いです。
このままでは、塗料がしっかり付着しないため、最初に、高圧洗浄機などで壁面をきれいに洗浄します。
こびり付いた泥やカビは、デッキブラシで擦り落とし、洗浄後は十分に乾燥させましょう。
次に、ケレン作業と呼ばれる研磨処理を行います。
ケレンとは、ヤスリや工具で古い塗膜やサビを落とす下地調整作業のことで、木部ではサンドペーパーを使った研磨が中心です。
荒め(#80~#100程度)の紙やすりで木肌の毛羽立ちや浮いている旧塗膜を削り落とし、表面を滑らかに整えます。
古い塗膜が剥がれかけている部分は皮スキやスクレーパーで完全に除去してください。
また、ひび割れて隙間ができている箇所には木工用の充填材(木部用パテ)を詰めて平滑にしておきます。
下地処理をしっかり行うことで、後から塗る塗料の密着性が格段に高まります。
ケレンに関して、詳しくは、こちらの記事もご覧ください。
2. 養生作業

下地処理が完了したら、塗装の前に周囲を養生します。
塗料が飛び散ったり垂れたりしても良いように、窓や扉、床や植栽など塗らない部分を、ビニールシートやマスキングテープで覆います。
木造住宅の場合、軒天井や破風板など、他の木部との取り合い部分もあるので、細部まで丁寧に養生を施すことが綺麗に仕上げるコツです。
養生作業を怠ると、仕上がりに塗料のはみ出しができたり、後片付けが大変になりますので注意しましょう。
3. 下塗り(プライマー)

塗装工程では、まず下塗りから始めます。
木部用の下塗り塗料(プライマー、シーラー)を塗布し、木材の内部までしっかり浸透させます。
下塗り材には、木材の吸い込みを抑えて、上塗りを密着させる働きがあり、塗装の土台となる非常に重要な工程です。
ムラなく均一に塗り広げ、木材の隅々まで行き渡らせましょう。
下塗り塗料が乾燥した後、場合によっては細かな研磨を行います。
下塗りによって、再度、木の繊維が立って、ザラザラすることがあるため、#240程度の細かいサンドペーパーで軽く表面を擦り、微細な毛羽を取って滑らかにします。
このひと手間で、仕上がりの肌触りが良くなります。
4. 上塗り(仕上げ塗装)

続いて、上塗り工程です。
下塗りが完全に乾いたら、仕上げ用の塗料を塗っていきます。
使用するのは下塗りと相性の良い木部用上塗り塗料です。
ローラーや刷毛を使い、厚みが均一になるよう丁寧に塗り広げます。
屋外の木造住宅の外壁は、常に過酷な条件に晒されるため、多くの塗料メーカーでは、上塗り2回塗装することを推奨しています。
1回塗っただけでは、膜厚が不足し、耐久性や発色が不十分になるためです。
少なくとも2回重ね塗りして、塗膜に十分な厚みを持たせましょう。
各塗り工程の間は、塗料が指触乾燥するまで数時間以上あけ、下の層を傷めないよう配慮します。
晴天で湿度が低い日でも、急いで重ね塗りすると、仕上がりに悪影響が出るので、乾燥時間は守ることが重要です。
なお、ステイン系塗料を使う場合は、下塗りの段階からステインで処理します。
造膜型塗料のような専用プライマーは不要で、代わりに、1回目から木材用ステインを塗り込んでいきます。
その後、希望の色合いになるまで、数回ステインを塗り重ね、最後に、耐候クリアーを塗って仕上げる方法もあります。
いずれの場合も、塗装後は塗料が完全に乾くまで外壁を触ったり雨に濡らしたりしないよう注意しましょう。
5. 点検と仕上げ

上塗り塗装が完了したら、塗り残しやムラがないか最終点検を行います。
光の当たり方で、色ムラがないか、木目の隙間まで塗料が行き届いているかなど、様々な角度から確認しましょう。
問題がなければ、養生を全て剥がし、周囲を清掃して作業完了です。
万一、乾燥中に虫やゴミが付着して塗膜に埋まってしまった場合は、部分的に、再度、塗り直して仕上げます。
なお、塗り終わった後、余った塗料が出ることがありますが、そのまま排水口に流すのは厳禁です。
塗料用の凝固剤(固化剤)を混ぜて固めるか、新聞紙やウエスに染み込ませて、可燃ごみとして廃棄してください(自治体によって異なる可能性があります)。
使用した刷毛やローラーも、水性塗料なら水で洗い、油性塗料ならシンナーで洗浄しておきます。
◆ 塗装に必要な道具類

以上が基本的な塗装の流れですが、DIYで実践する場合は、工具や資材もあらかじめ用意しておきましょう。
- 高圧洗浄機(またはホース、ブラシ)
- サンドペーパー(#80~#100、#240など複数種)
- 皮スキ・スクレーパー(古い塗膜剥がし用)
- 養生シート、マスキングテープ、新聞紙
- 刷毛(はけ)、ローラー、ローラー用バケット(受け皿)
- 塗料缶、希釈用シンナー(水性なら不要)
- 手袋(ビニール手袋がベスト)、保護メガネ、防塵マスク
- 脚立、必要に応じて足場(ローラー延長棒も便利)
- ウエス(いらない布)や雑巾(掃除用)
- 塗料凝固剤(余った塗料の処分用)
これらを準備しておけば、おおむね外壁塗装作業に対応できます。
特に木部塗装では、下地処理の出来が仕上がりを左右します。焦らず丁寧に段取りを踏みましょう。
DIY初心者の場合は、いきなり2階建て全体を塗るのではなく、まず、1階部分やウッドデッキなど、手の届きやすい範囲から挑戦するのもおすすめです。
安全第一で進め、無理だと感じたらプロに相談する勇気も大切です。
次章では、DIYとプロのどちらに依頼するべきか、それぞれのメリット・デメリットを見ていきます。
木造外壁塗装にかかる費用相場

木造住宅の外壁塗装にどれくらい費用がかかるかは、多くの施主様が気になるポイントでしょう。
塗装費用は、主に塗装面積、使用する塗料の種類、建物の高さ(足場の必要性)、外壁の劣化状態などによって大きく変動します。
そのため、一概に「木造だから高い・安い」とは言えませんが、目安となる相場を以下に紹介します。
プロに依頼した場合の費用相場

塗装専門業者やリフォーム会社に依頼した場合、費用は見積もり次第ですが、30坪程度(延べ床面積が約100㎡)の一般的な木造2階建て住宅で約80万~120万円が一つの相場です。
この中には、高圧洗浄・下地処理・養生・塗料代・人件費・足場代・清掃など工事に必要なすべての工程費用が含まれています。
実際の金額は、家の大きさや形状によって変わり、例えば平屋で低い建物なら足場が簡易で済む分安くなりますし、逆に3階建てや、外壁の凹凸が多い凝った造りの家では、手間が増え高額になります。
また、選ぶ塗料のグレードによっても値段が上下します。耐用年数の長い高級塗料は材料費が高く、全体費用も上がります。
木造住宅の場合、モルタルやサイディングの家と比べて特別に大きな割増費用がかかるわけではありません。
ただし、木部特有の傷み(腐食部分の板の交換や、細かな木材補修)が必要な場合、別途補修費が加算される可能性はあります。
その点、見積書の内訳に、木部補修費や大工工事費などの項目があるか、確認すると良いでしょう。
総じて言えるのは、劣化がひどくなる前に塗装しておけば、追加補修費なしで済み、費用を低く抑えられるということです。
DIYで塗装する場合の費用

一方、外壁塗装をDIYで行う場合の費用は、必要な材料と道具を揃えるコストになります。
主な内訳は、塗料代と道具代です。
30坪程度の木造住宅全体を塗るには、下塗り材と上塗り材を合わせて8~20万円前後の塗料代がかかるのが一般的です。
塗料の種類やグレード、購入先によって価格は変動しますので、ホームセンターやネット通販でよく比較しましょう。
さらに、初めて塗装を行う場合、刷毛・ローラー、養生シート、洗浄用具などの道具類を一から揃える必要があり、別途4~10万円程度の費用が見込まれます。
特に、高圧洗浄機は購入すると数万円しますが、レンタルするという方法もあります。
以上を合計すると、30坪クラスの住宅をDIY塗装する場合でおよそ12~30万円前後がひとつの目安となります。
ただし、これは足場代を含まないという点に注意が必要です。
2階部分を塗るには、安全に作業できる足場が必要ですが、個人で足場を設置するのは危険ですし、業者に依頼して組んでもらうと、10~20万円ほど費用が発生します。
足場を使わず脚立だけで済む範囲(1階部分や低い塀など)の塗装に留めれば、DIYでも問題ありませんが、家全体を自力で塗るのは現実的に難易度が高いことを覚悟しましょう。
また、高所作業には落下などのリスクが伴うため、無理は禁物です。
DIYに関しては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
自治体の補助金制度の活用

塗装費用を抑える方法として、お住まいの自治体の補助金を活用できる場合があります。
市区町村によっては、「住宅リフォーム助成金」「耐震改修補助金」などの名称で、外壁塗装工事に一定額の補助金や支援金を出していることがあります。
例えば、「外壁塗装工事に対して上限○万円まで補助」といった制度で、条件として地元業者に依頼する、工程写真の提出が必要、予算枠がなくなり次第終了、など制約があるのが一般的です。
それでも、10~20万円前後の補助を受けられるケースも多く、利用しない手はありません。
お住まいの地域でどんな補助制度があるかは、自治体の公式ホームページや担当窓口に問い合わせると確認できます。
また、住宅リフォーム支援制度検索サイトを利用すれば、全国の地方公共団体が実施するリフォーム補助制度を調べることも可能です。
工事契約の前に要件を満たすか確認し、ぜひ申請を検討してみてください。
外壁塗装の補助金や助成金に関しては、こちらの記事にも詳しく解説しています。
なお、経年劣化ではなく、台風や雹災など災害による外壁の破損であれば、火災保険が適用できる可能性があります。
「保険を使えば無料で塗装できる」といった営業トークもありますが、実際には保険会社の認定基準が厳しく、誰でも使えるわけではありません。
あくまで、自然災害で生じた損傷の修復費に限って保険金が下りる場合がある、ということだけ念頭に置いておきましょう。
外壁塗装の火災保険に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。
木造外壁塗装はDIYとプロどちらにすべきか

ここまで、木造住宅の外壁塗装について解説してきましたが、実際に施工する際に迷うのが「DIYで自分で塗るか、プロに任せるか」という点ではないでしょうか。
結論から言えば、仕上がりの品質や安全面を重視するなら、当然、プロに依頼するのがおすすめです。
しかし、予算を抑えたい、DIYが趣味で、ある程度の腕に自信がある、といった場合にはDIYに挑戦する選択肢もあります。
ここではDIYとプロ、それぞれのメリット・デメリットを整理してみましょう。
DIYで塗装する場合

DIYのメリットは、何と言っても、費用を安くできることです。
前述のように、道具代や材料費はかかりますが、施工にかかる人件費をゼロにできます。
家族や友人と協力して作業すれば、業者に依頼した場合の半額以下で外壁を塗り替えられる可能性もあります。
また、自分のペースで進められるので、時間をかけて、納得いくまで作業できる点も魅力です。
仕上がりの色味や風合いも、自分で調整しながら施工できます。
うまく完成したときの達成感もDIYならではでしょう。
一方、DIYには、デメリットも多々あります。
まず技術や知識が必要なことです。
外壁塗装は、単に色を塗るだけでなく、下地処理や塗料の希釈、天候の見極めなど専門的なノウハウが要求されます。
慣れない人が行うと、塗りムラができたり、十分な膜厚を確保できずに、塗り漏れが発生したり、最悪の場合は、短期間で塗膜が剥がれてや、再度塗装をしなければならないということもあります。
また、高所での作業は危険が伴います。
脚立のバランスを崩して転落したり、屋根から落ちる事故も実際に起きています。
プロは慣れていますが、素人が高さ数メートルで長時間作業するのは想像以上に不安定で疲労するものです。
さらに、作業に時間がかかる点も大きなデメリットでしょう。
プロなら、足場架設から塗装完了まで、10日前後で終わる規模の工事でも、DIYだと週末だけの作業では、数ヶ月かかることもあります。
その間、養生シートに覆われた家で不便な生活を強いられる可能性もあります。
加えて、作業中や完了後に、なんらかの不具合が起きても、自己責任となる点も留意が必要です。
雨漏りが発生しても、保証してくれる業者はいません。
DIYに関しては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
プロに依頼する場合

プロの業者に任せるメリットは、何と言っても仕上がりの確かさです。
豊富な経験を持つ職人が施工することで、美しく耐久性の高い塗装に仕上がります。
下地処理から細部の納まりまで、プロならではの丁寧な仕事で安心して任せられます。
また、工期も計画的に進むため、天候にもよりますが、戸建て住宅なら約2週間程度で工事が完了するのが一般的です。
さらに、安全管理もしっかりしています。
適切な足場を組み、安全帯を使用し、複数人で協力して作業するため、事故のリスクを最小限に抑えています。
使用する塗料や工程についても、プロの目線で最適な提案をしてくれるでしょう。
保証が付くのも安心材料です。
施工後に万が一、不具合が見つかった場合でも、保証期間内であれば、無償で手直ししてもらえるケースが多く、アフターフォローも期待できます。
プロに依頼するデメリットは、やはり費用がかかることです。
人件費・経費がかかる分、DIYに比べて、工事費用の総額は高額になります。
ただし、塗装業者ごとに価格やサービス内容は異なるため、相見積もりを取って比較検討することで、納得できる価格で依頼できる可能性もあります。
もう一点は、自宅の外壁塗装を、どの業者に頼むか選定が難しいという点です。
そもそも外壁塗装を行う会社が多いことだけではなく、残念ながら、悪徳な外壁塗装業者も存在し、素人には見積もりの妥当性や技術力の違いが判断しにくい面があります。
この点は、信頼できる業者紹介サイトや、実際に施工を依頼した知人の口コミなどを参考に、慎重に選ぶことでカバーしましょう。
総合すると、「費用を抑えたい」「DIYを楽しみたい」という方以外はプロに任せるのが無難です。
特に、2階以上の塗装は危険が伴うため、安全と品質を優先するなら、迷わず専門業者に依頼しましょう。
その際は、複数の業者から見積もりを取り、提案内容や価格を比較して納得のいく契約を結ぶことが大切です。
外壁塗装をプロにお願いしたい場合には、以下の記事でも詳しく解説しています。
- 外壁塗装はどの会社に頼むべき?優良業者の選び方と失敗しないポイント
- 外壁塗装の優良業者を探す時のコツ
- 外壁塗装に潜む悪徳業者の実態|よくある手口と対策方法
まとめ

木造住宅の外壁塗装について、要点を最後にまとめます。
- 木造外壁の魅力は、自然な木目と温かみですが、雨・湿気・虫・紫外線に弱いため、定期的な塗装メンテナンスが必要不可欠です。塗装することで、防水・防腐・防虫効果を付与し、木材の劣化を防ぎます。
- 劣化のサインとして、色あせ、チョーキング、塗膜剥がれ、ひび割れ、カビ・藻、シロアリ被害などが挙げられます。こうした症状が見られたら、塗り替えどきです。木部は塗膜の寿命が短いため、5年程度を目安に、早めに塗装を検討しましょう。
- 塗料選びは木造外壁塗装の要です。木部専用かつ屋外用の塗料を使用し、防腐・防蟻・UVカット効果のある製品を選ぶと安心です。木目を活かす浸透型(ステイン)と、塗膜で覆う造膜型(ペンキ)から目的に応じて選択しましょう。木材への塗装は3~5年ほどで劣化するため、耐久年数よりも、柔軟性やメンテナンス性も考慮することが大切です。
- 塗装作業の手順は、洗浄→研磨(ケレン)→養生→下塗り→上塗り(2回)という流れが基本です。特に、下地処理を丁寧に行うことで仕上がりと耐久性が向上します。高所作業には、足場を用いるなど安全に配慮し、適切な気候条件の下で作業しましょう。
- 費用相場は、プロに依頼した場合、30坪程度で80~120万円前後が目安です。DIYなら、塗料・道具代で20万円前後に抑えられますが、足場を含まない点に注意が必要です。自治体のリフォーム補助金を活用すれば、10~20万円程度の支援が受けられる場合もあるため、情報収集してみましょう。
- DIY vs プロでは、品質と安全面ではプロに軍配が上がります。DIYは、費用節約や達成感が魅力ですが、技術や時間、リスクの面でハードルが高いことを認識してください。高所や広範囲の塗装はプロに任せ、DIYは、無理のない範囲で楽しむのがおすすめです。
木造住宅の外壁は、適切な塗装によるお手入れ次第で、美しさと耐久性を長く維持できます。
こまめなメンテナンスで大切なお住まいを守り、末永く木の温もりあふれる暮らしを楽しんでください。
塗装について不明な点があれば無理をせず、経験豊富なプロの業者に相談してベストな方法を検討することも大切です。
皆様の木造住宅の外壁塗装リフォームが成功し、住まいがより快適で魅力的になる一助になれば幸いです。