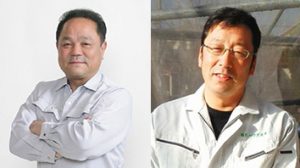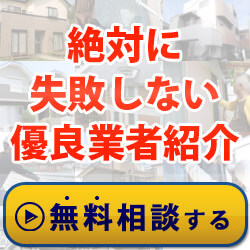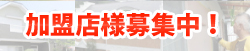本記事では、外壁塗装やリフォームに関する用語の内、「ね」から始まる用語を解説しています。
目次
根入れ深さ【ねいれふかさ】

根入れ深さとは、建物の基礎(構造部分)を地面に埋め込んだ時の深さのことです。
根入れ深さは、地面から基礎の底までの長さのことを表します。
根入れ深さを深くすると、建物の基礎が地面に深く刺さって、建物が安定させる力が増すため、根入れ深さは深い方が良いとされますが、地面をより深く掘る分、施工が難しくなります。
必要とされる根入れ深さは、
- べた基礎…12cm以上
- 布基礎…24cm以上
など、どの基礎で建物を建てるかで決められています。
建築物の基礎をべた基礎とする場合にあっては、
根入れの深さは、十二センチメートル以上
建築物の基礎を布基礎とする場合にあっては、
根入れの深さにあっては二十四センチメートル以上
(国土交通省 建築基準法から一部抜粋)
(木を)寝かす【(きを)ねかす】

木を寝かす(もしくは寝かせる)とは、伐採した丸太を乾燥させることをいいます。
伐採したばかりの木は、水分を含んでおり、そのまま加工してしまうと、加工後に乾燥して変形や収縮を起こしてしまうため、加工する前に木を寝かせ、木の中にある水分を抜きます。
寝かして水分が乾燥した木材は、曲がりなどの木材の特徴が出てくるため、木材は、寝かしてから適材適所の部材に使用されます。
木を寝かす方法には、
- 伐採した山の中でそのまま倒して乾燥させる「自然乾燥」
- 除湿乾燥室や乾燥機に入れて乾燥させる「人工乾燥」
などがあります。
根がらみ【ねがらみ】
根がらみとは、住宅の床を支える柱が倒れることを防ぐために設置する横長の板のことであり、根がらみ貫(ねがらみぬき)とも呼ばれます。
根切り【ねぎり】

根切りとは、建物の基礎や地下室などを設置するために、地面を掘ることです。
根切りには、
などの種類があります。
猫足【ねこあし】

猫足とは、椅子、テーブル、バスタブなどの家具の脚が、猫の足のように湾曲したデザインのことで、洋式の家具でよく見られます。
猫間障子【ねこましょうじ】

猫間障子とは、障子の一部にガラスがはめ込まれており、そのガラス部分にも開閉できる障子がついた障子戸のことです。
猫が障子を破らずに通れるように作られたことから猫間障子といわれますが、今では障子を開けた部分にガラスがはめ込まれています。
猫間障子には、
- 摺り上げ猫間障子
- 引き分け猫間障子
- 片引き猫間障子
などの種類があります。
ちなみにはめ込まれたガラスが常にむき出しの障子を雪見障子といいます。
ネタ【ねた】
外壁塗装におけるネタとは、塗料のことをさす言葉です。
根太【ねだ】

根太とは、フローリングなどの床板を支えるために、床板の向きと垂直に設置された長い木の部材のことです。
複数の根太を並べて設置し、その上にフローリング材などの床材を乗せて床を構成する工法を根太工法といいます。
ちなみに、根太を設置せずに分厚い床材を設置することで床を構成する工法を根太レス工法(剛床工法)といいます。
根太天井【ねだてんじょう】

根太天井(踏み天井ともいう)とは、昔の民家などに採用されていた天井の形式の一つで、一階天井に天井板を設置せず、二階の床を支える根太を露出された状態の天井のことです。
根太天井の場合、二階の物音が一階に響きやすいため、防音性を高めたい場合には不向きですが、例えば、二階が子供部屋であり、あえて防音性を下げるために根太天井を採用する場合もあります。
根太レス工法【ねだれすこうほう】
根太レス工法とは、根太を使用せず、下地に厚みがある合板を使用して住宅の床を作る工法のことであり、剛床工法ともいわれます。
根太工法の場合、幅が45mm以上の根太を合板の下に張り巡らせますが、根太レス工法の場合は、根太がなく、分厚い合板(24mm以上)で床を支えます。
根太レス工法は、
- 根太を必要としないため、施工時間が短く、施工費用も安い
- 横方向(水平方向)に対する力に強いため、地震や台風などで歪みにくい
などのメリットがありますが、
- 家の土台が少しでも歪んでいると床も傾いてしまう
- 床下に支える根太がないため、踏む場所によっては床がたわむ
などのデメリットもあります。
熱貫流率【ねつかんりゅうりつ】
熱貫琉率とは、「室内と屋外」などの温度差がある空間の間にある
- 屋根
- 窓
- 外壁
などの熱の伝えやすさを表す数値のことです。
熱貫流率の値は、
- 高いほど「屋外の気温は住宅内に伝わりやすい」
- 低いほど「屋外の気温は住宅内に伝わりにくい」
ということを表しています。
根継ぎ【ねつぎ】

根継ぎとは、柱の下部が古くなったり、腐ってしまったりした場合に、柱全体を交換するのではなく、補修箇所のみを新しい木材に交換するという伝統工法による補修のことです。
熱橋【ねっきょう】
熱橋とは、柱やコンクリートなどの断熱材ではない部分が、屋外の暑さや寒さを室内に伝えてしまう現象のことで、ヒートブリッジともいわれます。
建物の壁の中は
- 木
- コンクリート
- 断熱材
などで構成されており、木やコンクリートの柱などの「断熱材ではない部分」は、熱が通りやすいため、外の熱(暑さ、寒さのどちらも)を室内に伝えてしまい、冷暖房の効率が悪くなってしまいます。

図:熱橋のイメージ
NET金額 【ねっとぎんがく】
NET金額(NET価格ともいう)とは、業者が値引きを行った後の「顧客が支払う金額」という意味で工事の見積書などに使われます。
値引きなどをしていない金額をグロス金額(グロス価格)といいます。
ただし、NET金額という言葉には明確な定義がないため、業者によっては上記の意味ではない可能性があり、見積書に書いてあった場合は、その業者に意味を確認する必要があります。
熱膨れ【ねつふくれ】
熱膨れとは、外壁などの塗膜に熱による膨れができてしまう現象のことです。
塗装面の温度が何らかの原因によって急激に上昇することで、
- 下地に含まれる水分が水蒸気になる
- 仕上げに塗られた塗料の塗膜が軟化してしまう
などが発生し、1の水蒸気が2の軟化した塗膜を押し上げて膨れてしまうことで熱膨れが発生します。
熱膨れが悪化すると、膨れ上がった塗膜が破裂し、その部分の下地には雨水や紫外線などが直接あたってしまうため、下地も劣化させてしまいます。
熱膨れが発生する原因は、外壁や屋根の表面温度の上昇であり、塗装の色が濃いほど温度が上昇しやすく、薄いほど温度が上昇しにくいため、白や淡色で塗装すれば熱膨れは発生しにくいといわれています。
しかし、外壁の塗膜が膨れるのは熱膨れによるものだけではないため、外壁に膨れが発生しているのを見つけたら、まずは外壁塗装業者に相談するのをおすすめします。
熱割れ【ねつわれ】
熱割れとは、住宅などの窓ガラスが、日光によって生じるガラス表面の温度差によって割れてしまうことです。
窓ガラスの内、日光が当たる部分は、日光の熱で温度が高くなり膨張しますが、窓枠の内側などの日光が当たらない部分は、低温のままで膨張しません。
窓ガラスの「日光の当たる部分の膨張する力」と「日光が当たらない部分の留まろうとする力」が窓ガラスの許容量を超えると熱割れが発生してしまうのです。
窓ガラスにおいて熱割れは端から起こる場合がほとんどなので、
- 端からヒビが入っていれば熱割れ
- 端ではない部分から放射状にいくつもヒビが入っていれば物が当たったひび割れ
とおおよそ見分けることができます。
根巻き【ねまき】

根巻きとは、柱などの根本部分をモルタルで固めることです。
根巻は、地面と柱が接する部分をモルタルで固めるため、
- 柱の根本が雨水によって腐食することを防ぐ
- 土台が補強され、柱が倒れにくくなる
などの役割があります。
眠り目地【ねむりめじ】

眠り目地(めくら目地、突き付け目地ともいう)とは、石やタイルなどの部材同士をすき間なく敷き詰めることで目地を見えないようにした施工のことです。
眠り目地は、
- 石を積んで塀を作る
- 大理石のタイルで床を作る
などの時にに使われる手法です。
目地を目立たないようにするにはそれぞれの部材が、適切な大きさ、形である必要があるため、高い精度で部材を加工し、敷き詰める技術が必要です。
練付け【ねりつけ】
練付けとは、突板(つきいた。天然樹木を薄く削った板)などを合板に張り付けることです。
また、練付けが行われた板を練付板といいます。
高価な天然樹木のみで分厚い板を作ると、コストが高くなってしまいますが、練付けを行えば、天然樹木を使用するのは表面のみであるため、コストを抑えながら見た目の良い板を作ることができます。
練積み【ねりづみ】

練積みとは、石やブロックを積み上げる時に、部材同士のすき間にモルタルなどを接着剤として充填する積み方のことです。
練積みをした塀は安定するため、勾配や設置する地面によっては5mぐらいまで積み上げることができます。
ちなみに、モルタルなどを使用せずに石を積み上げる空積みの場合は、2m以上積み上げることは建築基準法施行令で制限されています。
練り箱【ねりはこ】

(画像引用:大和技研工業株式会社)
練り箱(練箱、練舟、トロ舟、プラ舟ともいう)とは、外壁塗装工事などで使用されるプラスチックでできた四角い容器です。
練り箱は、モルタルやコンクリートなどを作るために水や砂利を混合する時などに使用されます。
粘弾性【ねんだんせい】
粘弾性とは、粘性と弾性が合わさった性質のことです。
それぞれ複雑な性質ですが、簡単にまとめたものが以下です。
- 弾性・・・力を加えると伸びて、力を加えるのをやめると原形に戻る性質
- 粘性・・・力を加えると伸びて、力を加えるのをやめても原形には戻らない性質
- 粘弾性・・・力を加えると伸びて、力を加えるのをやめると原型には戻らないもののおおよそ元に戻る性質
粘度【ねんど】
粘度とは、液体の粘り具合のことで、外壁塗装でいえば、塗料でよく使われる言葉です。
- 粘り気があってネバネバしている状態を「粘度が高い」
- 粘り気がなくサラサラした状態を「粘度が低い」
と表現します。
外壁塗装用塗料において粘度は非常に重要で、
- 塗りやすさ
- 塗った後に垂れないか
などに影響します。
そのため、適切な粘度にするためにメーカーに定められた正しい希釈率で塗料を希釈する必要があります。
粘土瓦【ねんどがわら】

(画像引用:株式会社シバオ)
粘土瓦とは、粘土を瓦の形に成型し、高温で焼き上げた瓦のことです。
粘土瓦には、
- 陶器瓦・・・釉薬(ゆうやく。耐久性を高めたり、色を付ける塗り薬)を表面に塗って窯で焼く。釉薬瓦ともいう。
- 素焼き瓦・・・釉薬を塗らずに窯で焼く
- いぶし瓦・・・窯で焼いた後、煙によって燻す(いぶす)
など、製造方法の違いでいくつかの種類があります。
年輪【ねんりん】

年輪とは、木を切断した断面に見られる円状の模様のことです。
年輪は、
- 四季がある
- 乾季、雨季がある
などの気候の変化がある地域に生える木に発生します。
また、年輪は1年に一周ずつ増えるため、年輪を数えることで木の年齢が分かります。